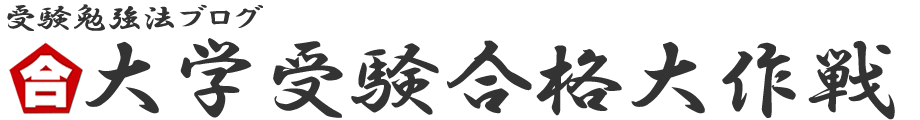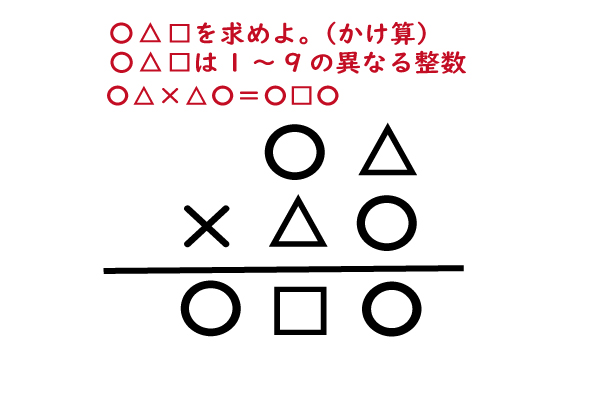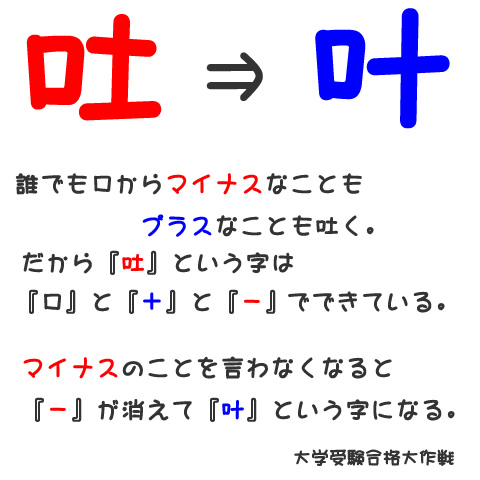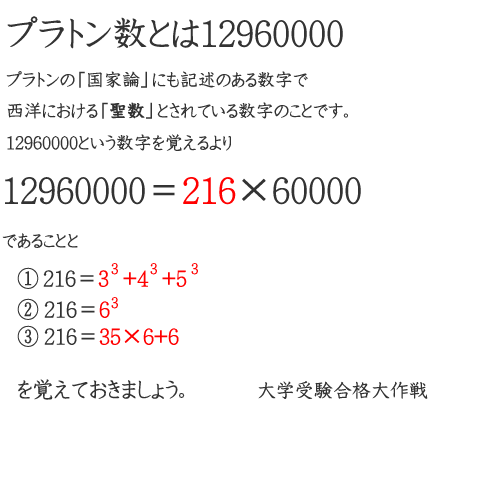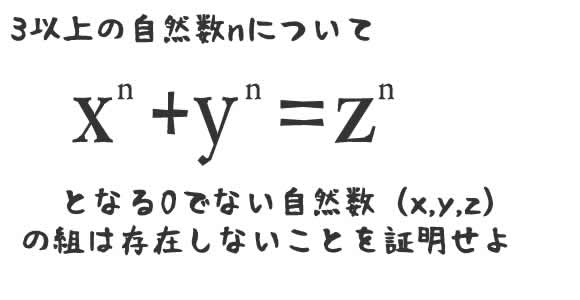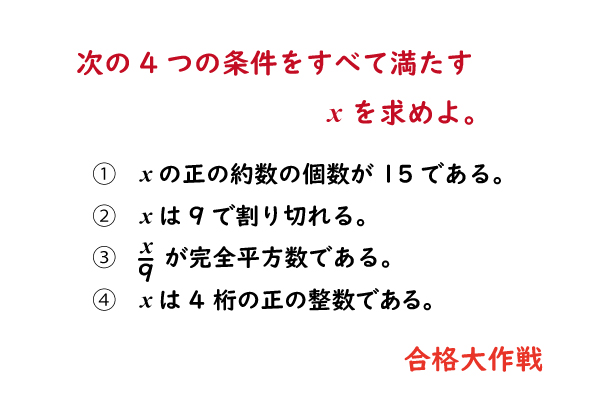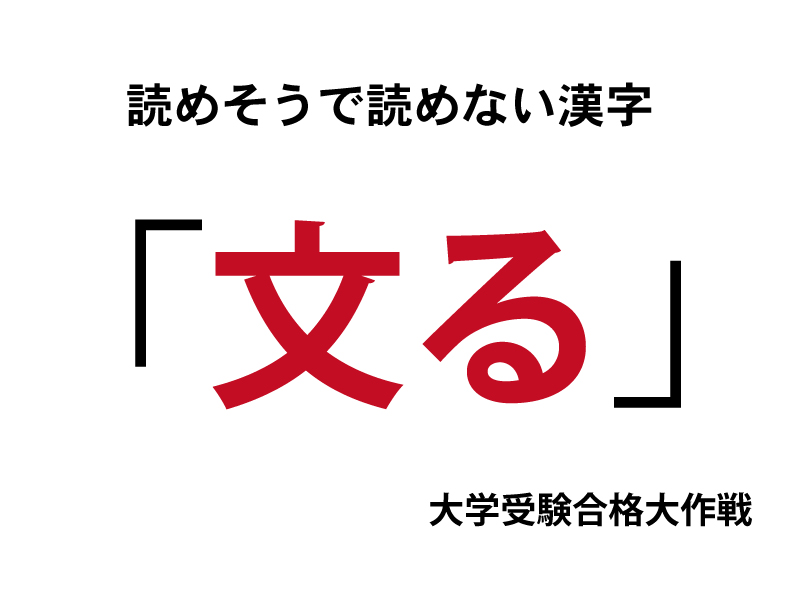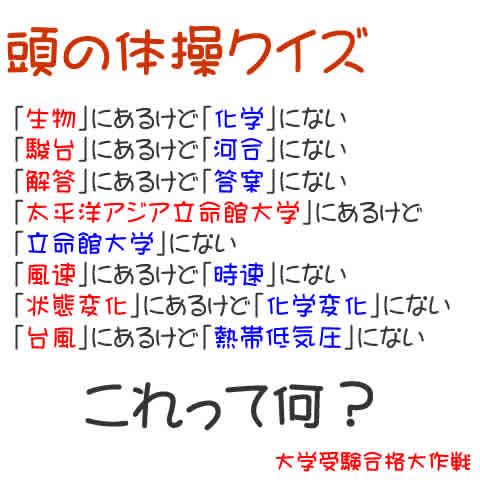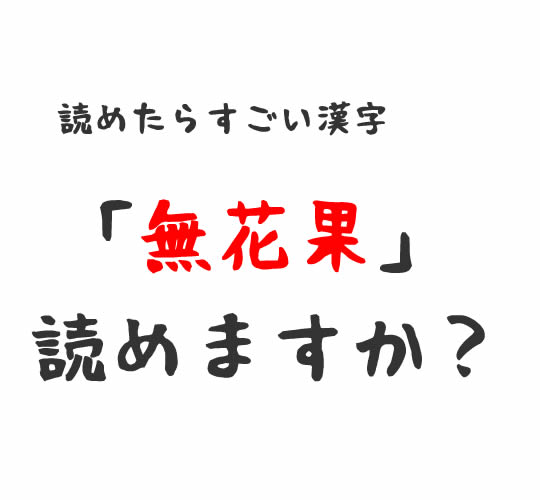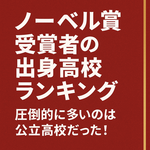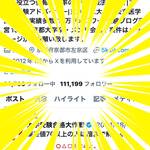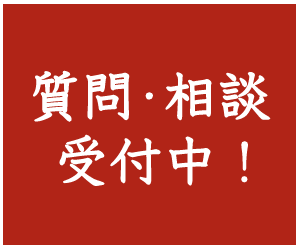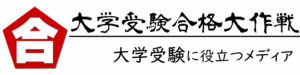本日は二十四節気の一つ「秋分」です。【国語のお勉強】
二十四節気とは1年を節分を起点として24に分割しそれぞれに季節を表す名称をつけたもの。
(節分とは立春・立夏・立秋・立冬の前日のことですが上の起点は立春のこと)
(1ヶ月の前半を「節」、後半を「中」と呼ぶ)
| 季節 | 名称 | 読み | 新暦 | 旧暦 | 説明 | |
| 1 | 春 | 立春 | りっしゅん | 2月4日頃 | 正月節 | 春のはじまり |
| 2 | 雨水 | うすい | 2月19日頃 | 正月中 | 雪は雨となり、氷も解けて水となる時季 | |
| 3 | 啓蟄 | けいちつ | 3月6日頃 | 二月節 | 冬篭りの虫などが暖かさ位誘われて地上に出てくる時季 | |
| 4 | 春分 | しゅんぶん | 3月21日頃 | 二月中 | 真東から昇った太陽は真西に沈み、昼と夜の長さが同じ | |
| 5 | 清明 | せいめい | 4月5日頃 | 三月節 | すべてがすがすがしく感じられ、草木の芽が出る時季 | |
| 6 | 穀雨 | こくう | 4月20日頃 | 三月中 | 穀物をうるおす春の雨が降る時季 | |
| 7 | 夏 | 立夏 | りっか | 5月5日頃 | 四月節 | 夏のはじまり |
| 8 | 小満 | しょうまん | 5月21日頃 | 四月中 | 植物がよく育ち茂る時季田に苗を植える準備を始める時季 | |
| 9 | 芒種 | ぼうしゅ | 6月6日頃 | 五月節 | 田に苗を植え始める時季 | |
| 10 | 夏至 | げし | 6月21日頃 | 五月中 | 北半球で昼の時間が一番長くなる | |
| 11 | 小暑 | しょうしょ | 7月7日頃 | 六月節 | 梅雨が明ける時季暑中見舞いを出す時季 | |
| 12 | 大暑 | たいしょ | 7月23日頃 | 六月中 | 一年中で最も暑い時期 | |
| 13 | 秋 | 立秋 | りっしゅう | 8月7日頃 | 七月節 | 秋のはじまり |
| 14 | 処暑 | しょしょ | 8月23日頃 | 七月中 | 暑さもおさまってくる時季 | |
| 15 | 白露 | はくろ | 9月8日頃 | 八月節 | 秋の気配が深まり、草木に朝露が宿る時季 | |
| 16 | 秋分 | しゅうぶん | 9月23日頃 | 八月中 | 真東から昇った太陽は真西に沈み、昼と夜の長さが同じ | |
| 17 | 寒露 | かんろ | 10月8日頃 | 九月節 | 秋が深まり、朝露の量も増える時季 | |
| 18 | 霜降 | そうこう | 10月23日頃 | 九月中 | 霜が降りるほど寒くなる時季 | |
| 19 | 冬 | 立冬 | りっとう | 11月7日頃 | 十月節 | 冬のはじまり |
| 20 | 小雪 | しょうせつ | 11月22日頃 | 十月中 | 雨が雪となり、寒くなる時季 | |
| 21 | 大雪 | たいせつ | 12月7日頃 | 十一月節 | 雪が降り積もる時季 | |
| 22 | 冬至 | とうじ | 12月22日頃 | 十一月中 | 北半球で昼の時間が一番長くなる | |
| 23 | 小寒 | しょうかん | 1月5日頃 | 十二月節 | 寒の入り。寒中見舞いを出す時季 | |
| 24 | 大寒 | だいかん | 1月20日頃 | 十二月中 | 一年中で最も寒さが厳しい時季 |

二十四節気は自然と季節の移ろいを肌で感じてきた我々の生活ときってもきれない関係があります。
二十四節気の知識があれば、古文を読み解く上でも受験生の大きな武器となるでしょう。
(二十四節気がそのまま和歌や俳句の季語として用いられることもあります。)
すべてを覚えておくのが理想ですが、理系の人や、効率を重視する人は次の八節(二至二分と四立)だけでも覚えておきましょう。
二至二分
- 夏至
- 冬至
- 春分
- 秋分
四立
- 立春
- 立夏
- 立秋
- 立冬
受験生へのメッセージ
本日は秋分の日。季節の変わり目は体調を崩しやすい。体調管理も重要ですよ!
⇒受験で勝利するために絶対おさえておきたい「受験生の体調管理方法まとめ」。受験は長期戦ですよ!!
それではまた明日!!
関連記事